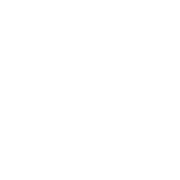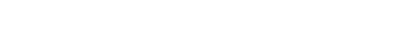お寺の手帖
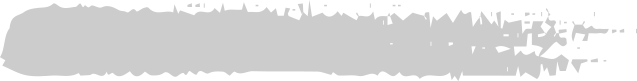
「お寺の手帖」は暮らしの中で役に立つお寺の知識や、宗派や尊像など、
みなさまが興味をもたれるお話を当寺副住職がわかりやすく語ります。
今月の聖語
今月の聖語 令和2年10月
2020年11月1日(日)
法華経は
明鏡の中の
神鏡なり
日蓮聖人御遺文「神国王御書」
解説〜神鏡(しんきょう)〜
鏡の前に立ったとします。あなたの顔、映っていますよね。でも不思議に思いませんか?一番身近にありながら自分の顔は鏡を通さないと見ることができません。
同様に私たちの生き様自体も自分では見えているようで実は見えていません。私たちの姿がありのままに見えているのは仏さまのみです、その仏さまの目を「神鏡」というのです。
そんなわたしたちが「神鏡」に映った我が身を見る術は、素直な心で一心に仏さまに手を合わせる。この一点に尽きるのです。
日蓮聖人ご遺文「神国王御書」
本書は「神国」とあるように、冒頭、天神七代・地神五代の流れを受け継ぐ日本に、仏教が伝来した経緯から説き起こされます。
その尊き縁をいただく国でありながら、なぜ内乱が起きるのかを究明され、その原因は仏法の乱れが人心の乱れを引き起こし、下剋上の世を招いたと指摘されています。
人びとの心の鏡になるべき教え…。すなわち法華経という「神鏡」に心を照らすべきことを強く訴えられているのです。
文永12年(1275) 聖寿54歳
今月の聖語 令和2年9月
2020年10月1日(木)
人には不孝が
おそろしき事に候ぞ
日蓮聖人御遺文「不孝御書」
解説 〜「孝」は潤滑油〜
「父」の字の成り立ちは一説には手斧を持って大地を切り開く姿を表現し、「母」はその大地で子を育む乳房を表すとか。一方「子」は大地から少し頭を出し、どんどん頭髪が伸びる様子を示しているともいわれてます。
しかし昨今の世相を見るとその字に込められた思いが忘れられているように思えてなりません。
その原因の一つは親ならこうしてくれるはず、子ならこうあるべきとお互いが勝手に作り上げた理想像を押し付け合っているためではないでしょうか。
この関係の潤滑油には「孝」があるでしょう「孝」の成り立ちは成長の極みを表した「老」から生まれたとか。
不孝は不幸の始まり。先人の思いを振り返りたいものです。
日蓮聖人ご遺文「不孝御書」
本書は四条金吾頼基氏に与えられた「陰徳陽報御書」の一部であったといわれています。
聖人の言われる「不孝」とは人倫の親子関係に留まるのではなく、一切衆生の真の親である本仏釈尊の慈悲に気づかずに背くこと。それが最も重い罪になると戒めておられます。
弘安元年(1278) 聖寿57歳
(弘安2年 聖寿58歳説あり)
今月の聖語 令和2年8月
2020年9月1日(火)
花は根にかへり
真味は土にとどまる
日蓮聖人御遺文 「報恩抄」
解説 〜共栄〜
日蓮宗では仏壇の過去帳の冒頭に次の言葉を記すことがあります。「先祖は樹木の根なり。子孫はその枝葉なり。根を培い養わずして枝葉栄える理なく、花咲き実生ずるためしなし。この過去帳は先祖代々の徳を報じ子孫永久の教えに備う」。
先祖と子孫の関係を木に例えるならば正にこの言葉の通りでしょう。さらにここから学ぶことは枝葉や花から取り込んだ養分も根に蓄えられ、さらに樹木全体が大きく成長するということです。すなわち先祖子孫一体となって共栄することが重要なのです。
日蓮聖人ご遺文「報恩抄」
真味とは功徳のことです。この一節は恩師・道善房への追善の結びに述べられています。
日蓮聖人の出家は父母、師匠への報恩も大きな目的でした。それは法華経信仰へと導くことだったのです。しかしその思いは遂に師匠ひは理解されず師弟の確執は生涯解消されませんでした。
こんな葛藤を抱えつつも、ひるむことなく法華経弘通ひ邁進された聖人の姿こそが、亡き師に捧げる真味となる報恩行だったのです。
建治2年(1276) 聖寿55歳
今月の聖語 令和2年7月
2020年8月1日(土)
いのちと申す物は
一切の財の中に第一の財なり
日蓮聖人御遺文「事理供養御書」
解説〜いのちの実感〜
いのちが尊いことは百も承知。しかし、それが心にドスンと落ち実感として響いていますか?
理解と実感は異なります。実感するのは身近で命の危険に直面した時ではないでしょうか。
「私たちは盤石の大地に立っている」と思うのは錯覚です。薄氷の上に存在すると知った時、それは何ものにも代え難い財と気付くのです。
日蓮聖人ご遺文「事理供養御書」
ある檀越から白米を送られたことへの礼状です。本書の末尾に「凡夫なれば寒も忍びがたく、熱もふせぎがたし。食ともし」の述べておられます。
聖人が身延に入って3年目。雪深く人が訪れることも少なく、ご自身のみならず弟子などを養う食物にも事欠くありさま。そこへ届けられた白米や芋の供養。いのちを繋ぐことができたことを感謝されています。
数多のご法難に加え身延入山後も常に死との隣り合わせだったからこそ、いのちの尊さを常に実感されていたのでしょう。
法華経こそがそのいのちを生かす根源であるの述べられているのです。
建治2年(1276) 聖寿55歳
今月の聖語 令和2年6月
2020年7月1日(水)
「父母は常に子を念へども
子は父母を念わず」
日蓮聖人御遺文「刑部左衛門尉女房御返事」
解説〜親の心子知らず〜
「老いて後思い知るこそ悲しけれこの世にあらぬ親の恵みに」。親御さんを亡くされた方、ぐっと来るものはありませんか?親が健在の時は「頑固なおやじ」「うるさいお袋」とつい愚痴っていませんでしたか?それが自分も年を重ねてくると、厄介と思っていたその親から受けた愛情、存在の重さに気づいてくるのではないでしょうか。
お釈迦さま、日蓮聖人ですら「未だ父母への孝養足らず」と懺悔しておられます。ましていわんや私達においては。
このお言葉をよくよく肝に銘ずべし!
日蓮聖人ご遺文「刑部左衛門尉女房御返事」
刑部左衛門尉女房とは尾張の住人の伝えられていますが詳細は不明です。
この女性が亡き母の13回忌に当たることから供養のためにと銭20貫文などを聖人に送ったことへの礼状です。
本書は父母の恩を語り「教主釈尊が父母孝養のために説かれたのが法華経である。日蓮も母上にかけた苦労を悔い、その償いと報恩は法華経による供養より他になし」と説かれています。
弘安3年(1280) 聖寿59歳
今月の聖語 令和2年5月
2020年6月1日(月)
先ず四表の静謐を
祈るべきものか
日蓮聖人御遺文「立正安国論」
今月の聖語 解説
〜信仰の寸心を改めよ〜
「疫れい、遍く天下に満ち広く地上にはびこる。死を招くの輩、既に大半を超え…」
これは日蓮聖人の代表著述「立正安国論」の冒頭のお言葉です。まさに800年前の様子が今私たちの眼前に起きています。
立ち止まってこのポスターを読んでくださっているあなた。あなたは多少なりとも宗教に更には日蓮聖人に関心をお持ちの方でしょうか。ならばそのあなたに伝えます。これは文字ではなく日蓮聖人の肉声であります。
この惨状の原因を「鬼神乱るるが故に万民乱る」と聖人は警告をされています。鬼神とは私たち人間が生み出すものです。医学科学実証主義の時代に笑止千万なと思われるでしょう。しかし、そもそもその思いがおごりだと言われています。
今一度謙虚に素直に聖人の声に耳を傾けて下さい。そして「南無妙法蓮華経」とお唱えしてみて下さい。それが世界(四表)に、日本に、そしてあなたに、安穏を取り戻す手立てなのです。
「立正安国論」
聖人の行動原理は総てこの書から発出しているのです。
文応元年(1260) 聖寿39歳
新型コロナウィルスの影響で大勢の方が苦しんだかと思います。また、大勢の方がお亡くなりになりました。まずはその方々の追善供養を祈らせて頂きます。
南無妙法蓮華経
緊急事態宣言が解除にはなりましたが、まだまだ気を抜いてはいけないと思います。
一人一人の行動が多くの皆様の命を救います。
どうぞ皆様お身体ご自愛頂き、また元気な姿でお寺へお越し下さいませ。よろしくお願い致します。
今月の聖語 令和2年4月
2020年5月1日(金)
善悪の根本
枝葉をさとり
極めたるを
仏とは申すなり
日蓮聖人御遺文「智慧亡国御書」
解説〜闇を切り裂く大灯明〜
「無明の闇」という言葉があります。
これは真理を照らす明かりがまったくなく真っ暗闇ということです。まさに迷いの根本です。
私たちはその中を手探りでさまよい歩いています。そして自分の価値観で「善だ悪だ」と決めつけ生きているのです。それがますます迷いを増長する結果となっているとも気づかずに…。
ならば私たちになくてはならないのは、闇を切り裂く灯明のはずです。その明かりとなるのは仏さまの智慧だけなのです。
本仏釈尊の前に素直に額ずく。これこそが大灯明を手にできうる唯一の方法なのです。
日蓮聖人ご遺文「智慧亡国御書」
本書は駿河の住人、高橋六郎兵衛入道の妻・持妙尼に宛てられたといわれています。
人間が抱える貪瞋痴の三毒の増長によって寿命が短くなっていく。更には様々な教えの流布がかえって国を亡びさせようとしていると警告されています。
それを救うのは唯一、善悪の根本を極めた本仏釈尊の智慧が明かされた法華経であると主張されています。
建治元年(1275) 聖寿54歳
今月の聖語 令和2年3月
2020年4月1日(水)
陰徳あれば
陽報あり
日蓮聖人御遺文「陰徳陽報御書」
今月の聖語 解説
〜陰徳陽報〜
「受けた恩は岩に刻め。貸した恩は水に流せ」と古人の言葉にあります。これは私たちの思いがこの反対になりがちだからこその戒めなのでしょうか。
見返りを考えずに行った親切でもお礼を言われなかったり、通じていなかった時に不満を覚える事はないでしょうか。
そんな時ちょっと振り返って下さい。あなただって誰かの親切に気付いていないことがあるかも知れませんよ。思い当たったらこの言葉を口ずさんで下さい。
「誰かがあなたの力になっている。あなたも誰かの力になっている。誰かが誰かの力になっている。」
日蓮聖人ご遺文「陰徳陽報御書」
本書は四条金吾氏に与えられたお手紙です。四条氏の強盛な法華経信仰は主君や同僚から何度も迫害を受けることになったのです。しかし相手の成仏を願う至誠の行動を貫いた結果、ついに事態が好転しました。
日蓮聖人は相手に理解されなくとも陰徳を積むことは必ずや大いなる功徳となって報われると説かれます。そのためにはじっと堪える忍辱心が重要なのだと励ましてくださってます。
弘安2年(1279) 聖寿58歳
今月の聖語 令和2年2月
2020年3月1日(日)
「娑婆と申すは
忍と申す事なり」
日蓮聖人御遺文「四恩鈔」
解説〜人生のアスリート〜
この世の人は娑婆とも呼びます。語源は梵語の「サハー」に由来し、苦しみを耐え忍ぶ世界ということです。
ところで今年は東京オリンピック・パラリンピック。アスリートたちは出場を目指し今まさに胸突き八丁。様々な思いで日々練習の苦しみに耐え忍んでいます。しかしその忍耐があるからこそ表彰台で光る涙がこぼれ落ちるのではないでしょうか。
苦しみは人の成長に導くエネルギー源です。私たちも人生の表彰台を目指すアスリートなのです。
日蓮聖人ご遺文 「四恩鈔」
本鈔は日蓮聖人伊豆流罪の折に書かれたお手紙です。
幕府に「立正安国論」を奏進するや次々起こる迫害の嵐。遂に伊豆流罪となられました。
しかし本鈔冒頭で「大いなる悦び」と語られるように流罪自体がご自身の法華経信仰の正しさの証しと受け止めておられます。そしてその迫害者たちに対しては「恩深き人」とまで述べておられます。
「忍」の極みに見えて来るのが「恩」なのです。
弘長2年(1262) 聖寿41歳
更新が遅くなり誠に申し訳ございません。
新型コロナウィルスが蔓延しております。皆様どうかご自愛頂き、お参りなどに来られる際は十分にご注意下さい。
よろしくお願い致します。
今月の聖語 令和2年1月
2020年2月1日(土)
心の財を
つませ給うべし
日蓮聖人御遺文「崇峻天皇御書」
解説〜怒りと付き合う〜
心の宝を傷つける根本に貪り、愚痴、怒りの三毒があります。この3つは互いに絡み合っていますが、なかでもまず生ずるのは怒りではないでしょうか。
最近は心理学でも「アンガーマネジメント」という怒りへの対処法の研究が行われています。それによればカッとした時、最初の6秒が重要だとか。その間、いかに心のコントロールをするかによって沈静するか増幅するかが変わってくるとのことです。
ところですでに仏様はそのコントロール法を用意して下さっていたのです。カッとしたら心の口で唱えて下さい。
「南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経」「はい6秒!」
今年の目標にしてみて下さい。
日蓮聖人ご遺文「崇峻天皇御書」
この書簡は堅固な信仰者、四条金吾氏に与えられた物です。金吾氏の欠点は非常に短気な点でした。いかに信仰が篤くとも短気は身を滅ぼす元になります。
この一節の前には「蔵の財よりも身の財すぐれたり。身の財より心の財第一なり」とあります。ここでの「心の財」とはひとえに忍辱の心を持つことでした。
建治3年(1277) 聖寿56歳