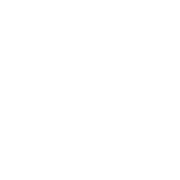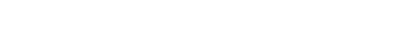お寺の手帖
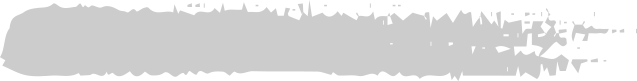
「お寺の手帖」は暮らしの中で役に立つお寺の知識や、宗派や尊像など、
みなさまが興味をもたれるお話を当寺副住職がわかりやすく語ります。
お塔婆の話
2019年8月4日(日)
今回はお塔婆についてお話ししたいと思います。
お塔婆は皆さまにもよく馴染みのある存在ではないかなと思いますが、最近流行りの樹木葬やロッカー式の方はあまりご縁がないのかと思います。
お塔婆は卒塔婆などとも言われており、起源はお釈迦様のご遺骨を安置する仏舎利塔が始まりとされています。
この仏舎利塔はインド映画やアラジンなんかで出てくるソフトクリームみたいな形の屋根の様な形をしており、その先端には死者が灼熱のインドで死者が暑さに苦しむだろうと、墳上に日除けの傘を立てる風習がありました。
さらに月日が流れ段々と高さがまし、日傘も亦その数を増し、三国時代中国に伝って中国独自の楼閣建築と結びついて、幾重かの基壇が重層塔の屋根となり、塔の本体である土饅頭は伏鉢としてその上に祀られ、多数の日傘は一本の竿に整理されて今の五重塔のような形になっていきました。
朝鮮を経て日本に伝って瑜祇塔(ゆぎとう)・多宝塔・三重塔・五重塔、あるいは石造の一三重塔が建造され「卒塔婆」は「塔」と称されるようになりました。
ここまで話をして「ん?お塔婆の話なのに建物の話ばっかり」と思われた方。
鋭い!
そうです。とてつもなく端的に簡単に偏見を持って一言で表すと
お塔婆を建てること=五重塔を建てること
となるのです。かなり強引ではございますが塔を立てることが供養となるのです。
お釈迦様は法華経の「如来神力品第二十一」というお経の中で「塔を建てて供養すべし」とお説きになられてます。
つまり塔の起源はお釈迦様のお墓である仏舎利塔ですから、お墓を建てることも、お塔婆を建てることもとてつもない徳を積むことに、ご先祖様や亡き方の供養になるのです。
最近、樹木葬や散骨なんて流行ってますけど上記のお経にも反してるわけですから私は心からお勧めしません。むしろ大反対です。
我々の生活も平屋の家から高層建築のマンションに変わったと同じく、お墓もロッカー式になることは構わないとですが、せめて一番上に塔があるものをお勧めします。デザインがどんなにダサくてもです。
と、お塔婆の話ではなくお墓の話で熱くなってしましましたので、戻します。
日蓮大聖人もお塔婆に関するご遺文が残っております。
弘安二年(一二七九)一一月三〇日、幼くして世を去った娘さんの十三回忌供養のため、佐渡から、身延の草庵を訪ねた中興信重に託して、故入道の未亡人に送られた『中興入道御消息』というご遺文があります。
ここでは、十三回忌追善供養に因んで、娘さんの未来の成仏を祝福され
「去(みまかり)ぬる幼子(おさなご)のむすめ御前(ごぜん)の十三年に、丈六のそとば(卒塔婆)をたてて、其面(おもて)に南無妙法蓮華経の七字を顕はしてをはしませば、北風吹けば南海のいろくづ(魚族)、其風にあたりて大海の苦をはなれ、東風きたれば西山の鳥鹿、其風を身にふれて畜生道をまぬかれて都率の内院に生まれん(略)此より後々の御そとばにも法華経の題目を顕はじ給へ」と教示されている。
簡単に説明すれば、「お塔婆の表にお題目を書いて供養すれば、そのお塔婆に触れた北風が南海にいる魚たちを供養して、また東風が吹けば西の山の野生動物もその功徳によって畜生道から抜け出せるだろう。これから後もお塔婆にもお題目を書いて供養してください」
といったような内容です。
ですからお塔婆というのはとても大切なんです。
法事や色々な法要でお建てになることがあると思いますが、その時にご当主だけでも構いません。できればご家族皆さまのお名前でお建てになったほうが家族皆さまがご供養をした、徳を積んだ、ご先祖様や亡き方にご供養の思いを伝えられたと言ったような気持ちになって頂けると思います。
今回はお塔婆のお話でした。