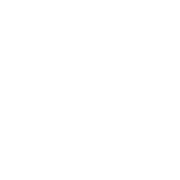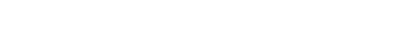お寺の手帖
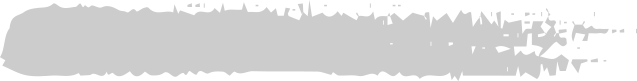
「お寺の手帖」は暮らしの中で役に立つお寺の知識や、宗派や尊像など、
みなさまが興味をもたれるお話を当寺副住職がわかりやすく語ります。
お彼岸
2019年3月19日(火)
暖かくなり春の訪れを感じる季節となりました。お寺の梅の花は咲き終わってしまってしまいましたが、通り沿いの河津桜は今を盛りと咲き誇っております。他にもしだれ桜や八重桜など桜も三種類ございます。春は出会いと別れの季節とよく言いますが、早速私にも出会いがありました。
それは花粉症です。
27歳にしてまさかの花粉症デビュー。
くしゃみがよく出るので風邪かな?なんて思っていたのですが熱は無く、鼻がムズムズして喉もイガイガ、そして目頭の痒みと顔全ての器官に支障を感じて日々生活をしております。
まだ薬には頼らず自然治癒力で完治してやろうと最後の悪あがきをしてます。
恐らく来年からは薬を貰いにいくと思われます。
私ごとはこの位にしておきまして、18日より一週間、お彼岸になります。
お彼岸の「彼岸」は、「到彼岸」という言葉に由来し、サンスクリット語の「パーラミター」を訳したものです。パーラミーターとは漢字で「波羅蜜多」と書きます。
三途の川を挟んで、こちらの世界を煩悩と迷いの世界である「此岸」といい、向こう側の世界を、悟りの世界「彼岸」へといいます。
その彼岸に到達するために、「六波羅蜜」(布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧)の修行を行い、彼岸はその修行をするための期間でもあります。
その期間に六波羅蜜の6つの修行を1日毎に行い、これを完結した人が7日目に川の向こう岸にある仏様の世界に行くことができるとされています。
この思想がやがて、我々日本人古来の風習や自然観、そしてご先祖様を崇拝するという習慣と結びついていくことで、今のお彼岸が生まれました。
お彼岸という期間は仏教の影響を受けていながらも、実は他の仏教国では設けられていませんし、ご先祖様を供養するというのも日本独自の風習です。
日本では、この期間には彼岸会の法要を行っているご寺院が多く存在します。宗派は問わず、お檀家様同士で集まってご先祖様を供養しお墓参りをするという日本古来のお彼岸の風習が根付いているのです。
ではなぜお彼岸とご先祖様の供養が定着したかというと、この時期になるとお盆と同じく帰省や里帰りをして先祖のお墓参りに向かう人が多くみられます。
また、春分の日や秋分の日は昼の時間と夜の時間が等しくなるとされており、我々の世界である此岸と仏様の世界である彼岸が最も近く通じやすくなる日であると理解されるようになりました。
次第に、春分の日と秋分の日に、ご先祖様の供養の法要を行えば、ご先祖様だけでなく自分自身にも功徳がくるとされ、またご先祖様への思いも最も通じやすくなるのではないかという思想が生まれ、お彼岸にはご先祖様の供養のためにお墓参りをするという行事が定着していったようです。暑さ寒さも彼岸まで、なんて言葉もあります。これから暖かくなって外出がしやすくなる季節となります。境内には、春に見頃となるお花がいっぱいございます。是非ご先祖様のお参りのついでにお花を楽しみにお越しください。お待ちしております。