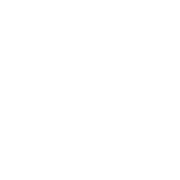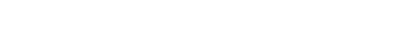お寺の手帖
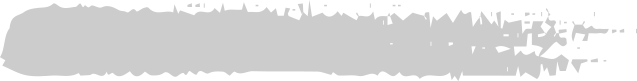
「お寺の手帖」は暮らしの中で役に立つお寺の知識や、宗派や尊像など、
みなさまが興味をもたれるお話を当寺副住職がわかりやすく語ります。
御会式(おえしき)について
2019年11月4日(月)
秋らしい気候になりましたが、日本各地の台風被害に遭われた方々の一刻も早い復興を願っております。
盛圓寺は墓石も倒れず、建物も被害なく何とか持ち堪えましたが、日蓮宗の寺院の多くは被害に遭われてしまっております。
そんな中でも台風19号が10月12日に関東に直撃しましたが、この日と次の日である10月13日は我々日蓮宗としてはとても大事な日でございます。
10月13日は日蓮聖人がお亡くなりになった日です。その前日はお逮夜(たいや)と呼ばれて、御入滅の地である池上本門寺様では万灯(まんどう)行列が各寺院から出され、屋台も出てお祭り騒ぎです。
ですから、これまでずっと何百年と続いてきた万灯行列も今年は未曾有の災害で行われなくなってしまいました。
私も18才から8年間学寮で行脚を行い参加しておりましたので大変残念です。
しかし、次の日の朝は台風一過で晴天の中万灯行列が行われたと聞いて安心いたしました。
日蓮聖人のお亡くなりになった日に行う法要を「御会式」と言います。
御報恩会式が短くなって御会式となり今年で738回目を迎える大切な法要です。
他にも御影講(みえいこう)、御命講(おめいこう)とも呼ばれ、安藤広重の浮世絵や松尾芭蕉の俳句の季語などにも出てくる事から昔から大切にされ、庶民の生活の一部となっていた事がよくわかります。
前説が長くなりましたが、去る10月27日に盛圓寺でも御会式法要を執り行いました。
毎年10月の最終日曜日が盛圓寺の御会式ですので皆様奮ってご参加頂きたくおもいます。
盛圓寺では毎年、花の会の方々が立派な生花を御奉納して頂きとても華やかに行います。
今年は私の希望(わがまま)で天井に紙で出来た花を飾ることによってさらに華やかさを感じる本堂になりました。
と言っても私は紙花を作りたいと言ったは良いですが、花は家内が夜通し作ってくれて、私は何もしないで口だけ出した結果になったのですが…笑
では、なぜ花を飾るのかと言うと、日蓮聖人が亡くなられた1282年10月13日に、季節外れの桜が咲き誇ったと言われる伝記をもとにしております。これを御会式桜と言います。
ですから、万灯でもこの花を至る所に飾って練り歩きます。
万灯の中に纏(まとい)があります。
纏と言えば、江戸時代に火事の時に屋根の上で纏持ちが消火活動の目印として振って士気を高めたものですが、纏を持たせたのは大岡政談で有名な大岡越前守様が始めさせたという話も残っております。
では何故、万灯と纏が関係するのかと言うと、江戸時代に団扇太鼓を打ち、お題目を唱えて行進するのを見て職人たちが法被姿で纏を担いで参加したのが始まりなんだとか。
後は、団扇太鼓はもちろん、チンチロチンチロ言う鉦や笛が入り、とても賑やかな行列になります。
昔は盛圓寺にも万灯講があり、昔の地元の方の話を聞けば秋祭りとして檀家であろうがなかろうが関係なしにみんなで纏を振ってお祭り騒ぎをしたという話を聞きます。
万灯講を復活させられれば、若い人にも御会式と言う法要、行事に興味を持って頂き、皆様で日蓮聖人の御命日に感謝の気持ちを捧げる事が出来るのかなと思っております。
この記事を読んでくださった皆様、もし興味があれば来年の10月12日の夜に池上本門寺様にお参りに行き、万灯行列を生で味わってみて下さい。
しかし、最近はかなりの方々が集まり、お祭り傾向に偏ってますので無法者のちらほら散見致します。
男性の方は喧嘩やスリ、女性の方はナンパに気をつけて頂きたいと思います。
盛圓寺万灯講復活を夢見て、本日の手帖はこの辺で終わりにしたいと思います。