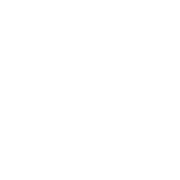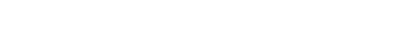お寺の手帖
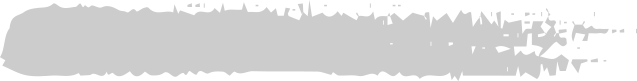
「お寺の手帖」は暮らしの中で役に立つお寺の知識や、宗派や尊像など、
みなさまが興味をもたれるお話を当寺副住職がわかりやすく語ります。
年回忌の話
2020年2月14日(金)
以前、お檀家様より
「何故、年回忌法要は毎年ではなく、3と7がつく年なんですか?」
とご質問がありました。
確かに一周忌から始まり、三回忌、七回忌、十三回忌と続いていきます。
それ以外のご命日は祥月命日といって、ご命日には変わりはないのですが、お寺で法要を行う方はあまり多くはございません。
本来ですと法要をして頂いた方が丁寧なのかとは思いますが、お寺に来て頂くという面でも費用の面でもご負担が大きくなります。ここ盛圓寺では、祥月命日忌の日にお塔婆を建てておいて下さいとのご依頼を良く頂きます。
故人を偲んでお気持ちを向けて頂けるのも、故人様の生前のご人徳、お人柄があってこそかと思います。
また一周忌は亡くなってから丁度1年の節目で行われる法要なので一周忌ですが、三回忌から七回忌と年回忌法要になっていきますと、数え年と同じ感覚で亡くなった時には既に1とカウントされます。
ですので丁度1年後に一周忌、丁度2年後に三回忌と言う数え方になります。
上の例に例えれば七回忌は亡くなってから丁度6年目に行う法要と言うことです。
話がそれましたが、では何故3と7の時なのでしょう。
諸説ございますが、この風習は日本で始まったものであって、仏教のもともとの風習ではないようです。
一つには十三仏信仰が関係しております。
十三仏とは初七日から三十三回忌までの、合わせて十三回の法要の守護仏です。
故人は、十三の仏様に守られて霊山浄土に導かれ成仏するとされています。
十三仏は、初七日 不動明王(秦広王)、二七日 釈迦如来(初江王)、三七日 文殊菩薩(宋帝王)、四七日 普賢菩薩(五官王)、五七日 地蔵菩薩(閻魔王)、六七日 弥勒菩薩(変成王)、七七日 薬師如来(泰山王)、百カ日 観音菩薩(平等王)、一周忌 勢至菩薩(都市王)、三回忌 阿弥陀如来(五道転輪王)、七回忌 阿閃如来(蓮華王)、十三回忌 大日如来(祇園王)、三十三回忌 虚空蔵菩薩(法界王)の事を指します。
これらの仏様が三回忌、七回忌、十三回忌、三十三回忌を守られていることから、3と7になったという説があります。
もう一つの説も、ただ適当にではなく仏教で大切にする数字になぞらえたと考えられます。
「7」は、お釈迦様がお生まれになったとき七歩お歩きになったという説も有名ですが、これは、私たちの迷いの姿である「六道」の世界を超えた悟りの世界に至る、ということを示しており、そこから「6」を超えた数字の「7」という数字が、迷いを超えるという意味で大切にされると言われます。
「3」も同じく、「2」を超えるという意味で、「2」を超えるというのは、「有・無」「勝・負」「損・得」というような両極端に偏った考え方を離れ、中道の生き方をするということを意味します。中道と言うのは、仏教でさとりを目指す上で大切な考え方であります。
お釈迦様も息子であるラーフラに、「二を超える生き方をせよ」とお教えになりました。そういう意味で「3」という数字も大切にされるそうです。
そこから毎年ではなく、せめて仏教で大切にする数字の年忌にお勤めしようということが習慣化し、「3」と「7」のつく年忌が行なわれるようになった、ということです。
地域によっては二十五回忌を行う場所もありますが、これはおそらく、回忌上げの五十回忌の半分というところからつけられたのかと思います。
年回忌法要や、「3」や「7」と言った数字の意味などをお教えしてきましたが、何よりも大切な事は、ご先祖様である故人様を偲んで思いや気持ちを向けて差しあげる事が何よりも一番大切です。
形だけやっても何の意味もなく、その回忌法要毎に自分のお爺ちゃんやお婆ちゃん、またはお父さんやお母さんの生前の姿を思い出しながら、感謝の気持ちを込めて手を合わせる。
お会いした事がないご先祖様でも、自分がここに存在していると言うことは、そのご先祖様がいらっしゃらなければ自分はここに居ないのですから、ありがとうと感謝の気持ち込めて手を合わせてあげて下さい。
法要を勤める私自身も一つ一つのご縁に感謝しながら、日々お勤めして参りますので、皆様もご一緒に手を合わせてお題目をお唱えして下さいましたら幸いです。
本日は年回忌のお話でした。