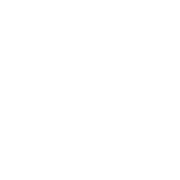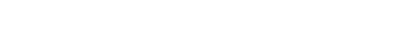お寺の手帖
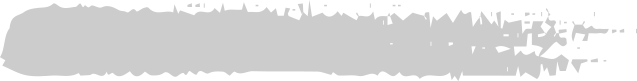
「お寺の手帖」は暮らしの中で役に立つお寺の知識や、宗派や尊像など、
みなさまが興味をもたれるお話を当寺副住職がわかりやすく語ります。
土用の話
2021年1月4日(月)
皆様、あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
去年はコロナでとても大変な一年でしたが、今年こそはいつも通りの日常が送れますように、皆様のご健康とご多幸をご祈念申し上げます。
1月はお正月から始まり、三ヶ日、松の内、七草、鏡開きなど、日にち毎に色々な行事が目白押しです。
皆様、1月17日は何の日だかご存知ですか?
そうです。冬の土用の入りです。
あれ?土用って夏だけじゃないの?
あれ?冬も鰻食べるの?
と、今にも聞こえて来そうですが、土用は夏のみではなく、春夏秋冬全ての季節の変わり目にあります。
また、鰻は無理に食べなくて結構です。
バレンタイン、クリスマス、土用etc…
色々な商法に惑わされないでください。
暴飲暴食せずに、旬なものを美味しく、バランス良く頂く。これが一番健康的かと思います。
話を戻しますと、上記の通り土用は季節の変わり目にあります。
また、土用は暦の雑節の一つで、他の雑節には節分、彼岸、八十八夜などがあります。
4つの土用のそれぞれは、春土用、夏土用、秋土用、冬土用とも呼ばれ、大体の目安としては次のようになります。
- 冬土用:1月後半~2月初め
- 春土用:4月後半~5月初め
- 夏土用:7月後半~8月初め
- 秋土用:10月後半~11月初め
詳しい日程はお寺のカレンダーに記載してますのでご確認下さい。
期間は大体18日間です。2週間ちょっとの間、土用が続きます。
では、どの様に土用が定められたのか?その由来についてみていきましょう。
土用は、中国の五行思想に由来しています。五行思想とは、万物は木・火・土・金・水の5つの元素から成り立っているとするもので、五行説ともいわれます。
そして、五行のそれぞれは次のように考えられています。
- 木 … 春の象徴
- 火 … 夏の象徴
- 土 … 「季節の変わり目」の象徴
- 金 … 秋の象徴
- 水 … 冬の象徴
このことから、先に述べた土用の期間が定められていて、「土旺用事」、「土用」といいます。
土用の期間中は、農作業や、土を動かす事、土木工事などは避けたほうがよいとされています。これは、土用は土公神という土の神様が支配する期間と考えられているからです。
とてもオーソドックスな説明をして来ましたが、わかりにくいと思いますので、私なりの解釈を述べてみたいと思います。
土用期間は、季節の変わり目と言いました。
ですから、土が冬→春へ、春→夏へ…と季節ごとの土に生まれ変わるのです。
ですから、今月の17日からは冬土用ですので、本格的に冬仕様の土に生まれ変わります。
生まれ変わると言っても、「はい、変わった!」と変われるものではありません。ゆっくりゆっくりシフトチェンジしていくものなのです。
しかも生まれ変わるには、前の土が一度腐り、その腐った養分から新しい季節の土が生まれます。
ですから、腐りかけているもの、腐っているものに触れる事になるので、控えたほうが良いとされてます。
では、その期間は畑も手入れしていけないのか?工事を進められないのか?と言う疑問が出てくると思います。
上記以外にも、2週間以上放置するわけにはいかない事も多くあると思います。
安心してください。全日程触れてはいけない訳ではありません。
「間日」と言うものがございます。
「間男」ではありません。(笑)
「マビ」です。
たとえ土用であっても間日であれば、土関係の事をしても支障はないとされます。この間日は季節ごとの土用によって、それぞれ次のように十二支の日で決められています。
- 春土用 - 巳・午・酉の日
- 夏土用 - 卯・辰・申の日
- 秋土用 - 未・酉・亥の日
- 冬土用 - 寅・卯・巳の日
です。
盛圓寺のお檀家様は、先日皆様にお配りした白い小さな冊子の「暦」でご確認下さい。
日にちに寅、卯、巳の書かれている日程は畑を思う存分、心置きなくいじり倒して下さい。
番外編ですが、土用とうなぎが何故リンクしたのか?ですが、
これは、江戸時代の学者、発明家など多くの肩書を持つ平賀源内によるといわれています。
もともと、『丑の日に「う」のつくものを食べると病気にならない』という言い伝えがあり、「うり(瓜)」「うめぼし」「うどん」などが良く食べられていました。
そして、鰻の旬が冬であることから、鰻の夏場の売り上げが伸びないことに困っていたうなぎ屋さんのために、源内が『本日 土用丑の日』というコピーをつくりました。
これが大当たりして、今に残っているのです。
一体、どれ程の宣伝広告費が源内さんに入って来たことやら…
それはさておき、他にも土用干し等色々な言葉にも土用と入ってきます。
昔から言い伝えられてる事には深い意味があります。他にもいろいろと調べると面白いかもしれません。
今回はそんな土用のお話でした。