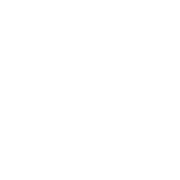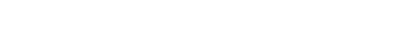お寺の手帖
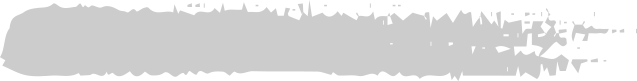
「お寺の手帖」は暮らしの中で役に立つお寺の知識や、宗派や尊像など、
みなさまが興味をもたれるお話を当寺副住職がわかりやすく語ります。
庚申塚
2019年2月1日(金)
昔、人の体の中に三尸(さんし)の虫というのが住んでおり、六十日に一度の庚申(こうしん)の日に人が寝てしまうと中から這い出し、天の神にその人の行状を報告しに行くという言い伝えがありました。そこで、これを信じる人たちが庚申の日は寝ずに夜通し語り合って、虫が外に出られないようにしようという集まりがありました。これを庚申待(こうしんまち)、庚申会(こうしんえ)といい、その仲間を庚申講(こうしんこう)といいます。もっとも、この集まりは純粋な信心のためだけでなく、娯楽の少なかった時代に飲食して一息つく口実だった面もあるようです。しかし、天の神を敬う気持ちが基にありますから神を祀るために石塔などを建てたものが庚申塚です。庚申待は元々、中国の道教の教えに始まり、祀る神も天帝、上帝という中国の神様でしたが、日本に入ると神道系では猿田彦、仏教系では青面金剛(しょうめんこんごう)または帝釈天(たいしゃくてん)になりました。
盛圓寺の庚申塚
柴又の帝釈天はあの「寅さん」でも有名ですね。盛圓寺の庚申塚に祀るのも帝釈天です。帝釈天は仏法守護の神で、四天王の上司です。庚申塚の石塔には大きく帝釈天王と刻まれ、その下に三匹の猿が彫られています。見ザル、聞かザル、言わザルです。つまり都合の悪いことは見なかったこと、聞かなかったことにして神様には言わないでくれ、というわけです。それなら、はじめから悪いことはしなければ良いのですが、そうもいかないもの。少しのことは見逃して下さいとの人情から生まれたサル達です。そのせいか、少しおどけた姿を是非、見てあげて下さい。しかし、帝釈天の目は欺けません。石塔の上部にはお日様とお月様も彫られています。つまり、昼も夜も神様には全部、お見通しです。